
心不全に合併する中枢性睡眠時無呼吸に対する
低侵襲治療デバイス開発
株式会社HICKY
代表取締役・共同創業者 林 健太郎 様
取締役・共同創業者 稲垣 大輔 様
取締役・共同創業者 近藤 佑亮 様
研究員・共同創業者 家城 博隆 様
株式会社HICKYは、医師2人、臨床工学技士1人、エンジニア1人の4人が共同で創業した会社で米スタンフォード大学発の医療機器開発プログラム「Biodesign」のフェローシップでチームを結成した。日本と米国をまたぐチーム体制で、心不全の患者さんの約4割もが合併する中枢性睡眠時無呼吸の治療デバイスの開発にAMDAPの支援を活用しながら取り組む。「頂上まではまだ2合目。設立当初よりもはるかに大掛かりなプロジェクトであることがわかったのは研究開発が進んでいる証拠」だと、いきいきとした表情から意気込みが溢れる。

林もともと私たちはスタンフォード大学で始まり、今は日本でも行われている医療機器開発プログラム「ジャパンバイオデザイン」の7期生として、臨床現場を観察して300件を超えるニーズを検討してきました。その一つが今回取り組んでいる「心不全に合併する中枢性睡眠時無呼吸に対する低侵襲治療デバイス開発」です。
中枢性睡眠時無呼吸は、睡眠時無呼吸の一種で、患者さんが眠っている間に呼吸のリズムが乱れたり、呼吸そのものが止まってしまう病気です。一般的な睡眠時無呼吸と異なり気道が閉塞するわけではないので、“いびき”もありません。心不全や脳卒中などが原因で発症しますが、今回の開発では主に心不全の患者さんにフォーカスしました。高齢者の10人に1人が心不全を患い、合併症として中枢性睡眠時無呼吸になるのはその4割と言われます。
心不全の患者さんの容態が悪くなり緊急入院する時間帯を見ると37%が夜中であることが報告されています。私と家城、稲垣は医療従事者として、実際に対応した経験がありますが、患者さんご本人だけではなく付き添うご家族の負担も大きいです。夜間の急患を減らせたら、医療機関にとっても患者さんとそのご家族にとっても負担はかなり軽減できるので、臨床的意義は大きいと考えています。
2015年頃までは治療法があったのですが、有効性が十分とは言えないという臨床研究が報告されました。否定されたまま有効な治療法が確立していない領域です。
近藤私たちが研究開発を進める低侵襲治療デバイスは、胸部の静脈に留置するステントに、横隔神経を刺激する装置を組み合わせ、その横隔神経刺激装置に体の外から無線で給電するというものです。ステントと神経刺激装置と無線給電とを組み合わせるような埋め込み型のデバイスを開発した経験のある会社は国内では見つからず、海外の技術動向を見ながら、試行錯誤しています。
胸部静脈に留置するステントも横隔神経刺激装置も、求めるメカニズムのデバイスは存在しますが、課題があることもわかっています。こうした課題を乗り越え、より低侵襲で使いやすくしようというのが私たちの目標です。
林私は小児外科医でプロジェクト全般を見ています。家城は循環器内科医でスタンフォードに留学して心臓病に関する研究をしており、このプロジェクトではカテーテルを使った動物実験などを担当しています。稲垣は臨床工学技士で、医療機器におけるQMSやスタートアップを立ち上げた経験もあることから資金調達、知財などの事業戦略を担当しています。近藤はエンジニアとしてプログラム医療機器の開発から認証まで携わった経験がありますし、チームの中でメディカルとエンジニアリングをうまく繋いでいます。
家城試作するデバイスの技術的な課題の解決と、米国展開の足がかりを掴んでいきたい。技術開発の課題の1つが無線給電です。ペースメーカーを例に挙げると、胸元に実装されたデバイスを想像されると思います。世界的にはリードレス化が進んでいて、体の外に本体を設置する必要がなくなりました。ペースメーカーに給電するためのリード線のトラブルがあったり、感染の問題が生じたりという課題があって、今ではカプセルのような小さなデバイスを心臓に直接入れるモデルも登場しました。私たちが参考にしていた横隔神経刺激装置も従来のペースメーカーと同じく有線での給電形式でした。有線であるがための電池交換などの煩雑さをなくすためにも、確立させたいのが無線給電です。
稲垣事業化に向けては、国内よりも米国での上市を先に狙う可能性は大きいです。FDAの方が新しい医療機器に対する薬事承認のプロセスが建設的であると聞きますし、世界で勝負をしたいのでFDAで承認を目指したいという思いもあります。
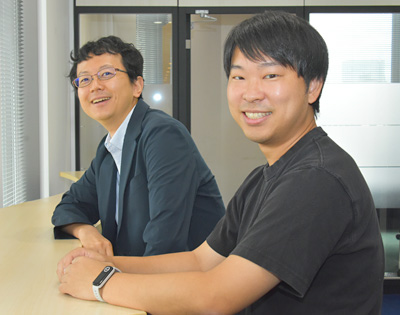
稲垣相談できる専門家の人数と専門性の広さが圧倒的な魅力だと思います。相談の内容によっては、専門家のネットワークも活用することができますし、医療機器開発に特化したアクセラレーションプログラムであることの恩恵は大きいです。
近藤ステントとデリバリーシステム、横隔神経刺激装置、無線給電とを組み合わせるタイプの高度管理医療機器ということもあり、明らかにすべきことは山積み。専門家に相談に乗ってもらいながら、次のアクションを決めていくわけですが、AMDAPがなかったら、今起きていることがもっと後ろ倒しになっていたと思います。大変ではありますが、プロジェクトの解像度は確実に上がっていると実感しています。
家城カタライザーとの面談が月に2回、専門家と月3回の面談をおこなっており、過密スケジュールな分、AMDAPそのものが私たちのペースメーカー的な存在になりました。
林開発も国内で完結させることに縛られる必要はなく、米国の医療機器メーカーとのコラボレーションに発展をさせたいと考えています。担当のカタライザーは、海外展開の知見があり、私たちが考える事業計画をしっかりと評価し、抜けている点を補い、異なる視点で意見を出してくれます。専門家との面談にカタライザーが出席して、会話を補完してくれることもよくあります。「この間のミーティングはこんな感じだったから次はこうしましょう」といった提案をいただくなど、本当にチームの一員として伴走してくれます。私たちは世界一のチームを作りたいという思いで取り組んでいますし、それに全力で応えてくれる。それがAMDAPの良さだと思います。