
有効な治療法がないがん性皮膚潰瘍を根本から改善し、
QOLの大幅な向上を図る
株式会社アドメテック
取締役 研究開発部長 中住 慎一 様
株式会社Carelogy
取締役CTO/医師 河本 直樹 様
株式会社アドメテックは、2003年に設立した愛媛大学発ベンチャーで、動物用の焼灼治療装置の製造販売を手掛ける。患部の温度をリアルタイムで測定して制御しながら、熱伝導で組織を熱変性させる技術を活かし、患者さんのQOL向上を目指そうとAMDAPで支援を受けている。カタライザーと専門家との面談を通して、アンメットメディカルニーズに挑戦する。
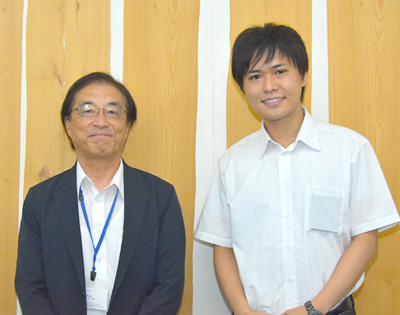
中住AMDAPの支援事業者として採択された当初は、「有効な治療法がないがん性皮膚潰瘍を根本から改善し、QOLの大幅な向上を図る」という開発テーマでした。がん細胞は正常組織に比べて熱に弱いという性質を応用した温熱療法の一つとして開発テーマを立てていました。患部に微細径の発熱プローブを穿刺し、がん組織や血管を加熱して凝固させるなど熱変性をさせて、皮膚表面に表れた患部からの滲出、出血、痛みやにおいを防ごうというものです。すでに国内では動物向けの医療機器として160施設に導入した実績があります。また、チェルノブイリ原子力発電所事故が起きたウクライナでは、現地の医療機関が主体となった臨床研究を経て医療機器として薬事認可を得ています。肝胆膵のがん患者さんを対象とする症例データが私たちの元に100件以上届いているので、現地では数百症例の治療がおこなわれていると思います。
がん性皮膚潰瘍は、乳がんや肺がんなどが皮膚に浸潤あるいは転移する症状で、患者さんとその家族にとって負担が大きく、QOLが著しく損なわれます。これを改善できないかとAMDAPに申し込んだわけです。そのための支援を受けるものと思っていたら、採択された早々から、私たちの特許技術で解決できる臨床ニーズについての協議がはじまりました。そもそも、私たちの技術は、元を辿れば愛媛大学の医学部と工学部との医工連携により実用化されたもので、臨床ニーズを解決するために確立した技術シーズと言えます。まったく別の産業で培った技術を応用するために臨床ニーズを探すという類とは少し性質が異なります。こうした背景がカタライザーの勘に働きかけたのでしょう。
河本医療機器開発と事業化に精通するカタライザーと、元PMDAに在籍していた消化器内科医といった医療従事者も専門家に加わり助言していただいています。その中で様々な角度からの意見や市場性についての考え方を学びました。候補に挙がった臨床ニーズは数多くありましたが、面談を重ねるうちに、自然と消化器(食道、胃、十二指腸など)の治療にフォーカスする方向でプロジェクトチームの合意形成がなされました。患者さんの食のQOL改善のための低侵襲治療に応用できるのであればその可能性に賭けたいとチーム全員の意思が固まり、今に至ります。
河本私たちがターゲットにしている疾患の1つは、食道がんに起因する通過障害の中でも重症度の高い「悪性食道狭窄」です。通過障害は、食道が狭くなり、食べたものが通りにくくなる症状で、食道がんは主な原因の一つです。外科的に患部を切除したり、放射線化学療法、食道バルーン拡張術、内視鏡ステント留置といった治療法はありますが、それぞれに再発や合併症などのリスクがあったり、治療を受けられる患者さんも限られたりと課題もあります。将来的には、膵臓がんの内視鏡的治療にも挑戦したいと考えています。
中住また、私たちと類似したがんを焼灼する治療法に、アルゴンプラズマ高周波焼灼・凝固療法があります。この治療法に対しては、患部の温度変化を捉え、必要な熱エネルギーを患部の内部に供給するよう制御するという私たちが特許を取得した技術で優位性を打ち出せるのではないかという評価を専門家の方々からもいただきました。
中住開発品は、侵襲が少なくて済むよう外径0.7mmの穿刺針に、その内側を外径0.4mmの電気ヒータを通す構造にしています。電気ヒータが穿刺針の先端部を発熱させ、患部への熱伝導で組織が熱変性する仕組みです。
河本これからは今の試作から、製品化に向けた設計、開発、実証試験が必要になります。目指すのはクラスⅡの医療機器での認証取得です。「一般的電気手術器」の性能に近く「再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器」の定義にも似ていますが、何に該当するかは、今後、PMDAとの相談になります。製品化するにしても、販路を開拓するにしてもクラスⅡを目指すのが妥当だろうと考えています。

河本開発テーマを変える方向に舵を切ることになりました。それは、とことん本質を掘り下げ、自社のコア技術をどのように生かせるかをしっかりと話し合うことができたからです。事業として考えた時に、「何に使えるか」ではなく、「何に絞るのか」を協議したことから、アンメットメディカルニーズへの方向が見えてきました。AMDAPは、まさに医学と工学の架け橋のような医療機器開発プログラムであるという印象を持ちました。
専門家には様々な診療分野の医師もいて、医療機器開発から事業化まで多彩な専門家に相談できるので人的リソースが限られる私たちにとっては極めて有用なプログラムです。最先端技術の機器でなくても、アンメットメディカルニーズに応えられる可能性があると教えてくれたのもAMDAPでした。しっかりと取り組んでまいりたいと思います。